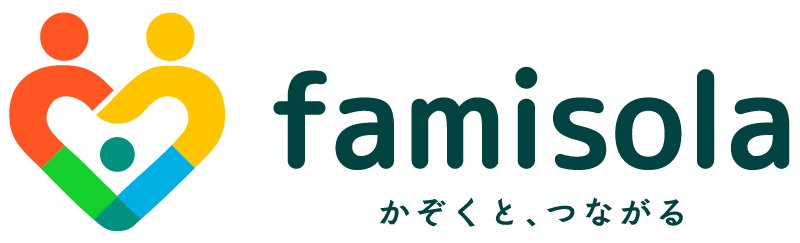「親に何かしてあげたい」という気持ちは、ふとした瞬間に芽生えるものです。しかし、いざ親孝行をしたいと思っても、何をすればいいのかわからずに迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。本記事では、親孝行とは何か、その意味を簡単に理解しながら、具体的に何をすればいいかのヒントをわかりやすく紹介していきます。
昔から「親孝行したいときには親はなし」ということわざがあるように、思い立ったときに行動することの大切さは、今も昔も変わりません。今回は、実際に親が嬉しかったと感じたことや、気持ちが伝わるプレゼントの選び方、日常の中でできる行動など、すぐに参考にできる親孝行の例を多数取り上げています。
さらに、ランキング形式で人気の親孝行アイデアや、親孝行の日にちなんだ過ごし方、家族で楽しめる旅行のおすすめプランなど、場面別に役立つ情報も盛り込みました。
大切なのは、形よりも気持ち。難しく考えず、自分にできることから一歩ずつ始めてみましょう。親子の時間をもっと心地よく、あたたかいものに変えるヒントがきっと見つかるはずです。
- 親孝行とは何かという意味を簡単に理解できる
- 具体的にどんな親孝行をすればよいかの例を知ることができる
- 親が喜んだ親孝行の体験談やプレゼントの選び方を参考にできる
- 無理なく続けられる親孝行のコツや旅行のおすすめを知ることができる
親孝行をしたいけど何する?おすすめのアイデア

ファミソラ・イメージ
- 親孝行とは。その意味を簡単に理解する
- 親孝行したいときには親はなしの教え
- 何する?例でわかる親孝行の形
- 親孝行されて嬉しかったこと体験談
- 気持ちが伝わるプレゼント選び
- 旅行 おすすめプラン3選を紹介
親孝行とは。その意味を簡単に理解する

ファミソラ・イメージ
親孝行とは、親に対して抱いている感謝の気持ちを、具体的な行動によって伝えることを意味します。これは決して特別な日に限ったことではなく、日々の暮らしの中で自然と行えることが大切です。高価な贈り物や盛大なサプライズを準備しなければならないというわけではありません。たとえば、仕事や家事の合間にふと「元気にしてる?」と声をかける電話を一本かけるだけでも、立派な親孝行になります。また、気づいたときに「いつもありがとう」と口にするだけでも、親にとっては心に残る言葉となるでしょう。
何よりも大切なのは、相手を思いやる気持ちが行動にしっかりと表れていることです。どんなに小さな行動でも、そこに愛情や配慮がこもっていれば、それはかけがえのない贈り物となります。たとえば、手書きのメモや小さなお土産、あるいは一緒に食事をする時間をつくることなど、日常の延長でできることがたくさんあります。親孝行は「してあげる」という一方的なものではなく、「一緒に過ごす」「気持ちを共有する」という相互的なコミュニケーションでもあるのです。
さらに、親との関係や家庭の状況、生活スタイルは家庭ごとに異なります。近くに住んでいて頻繁に会える人もいれば、遠方にいてなかなか顔を合わせられない人もいます。ですから、自分のライフスタイルに合わせた無理のない方法を選ぶことがとても重要です。たとえば、月に一度の連絡でも、継続して気持ちを届けることができれば、それは十分に意味のある親孝行になります。気持ちを押しつけず、自然体で続けていける関係性を築くことこそが、親子の絆をより深める鍵になるのです。
親孝行したいときには親はなしの教え

ファミソラ・イメージ
「親孝行したいときには親はなし」ということわざは、多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。この言葉には、親に感謝の気持ちを抱いたときには、すでにその親がこの世にいないという可能性がある、という深い意味が込められています。つまり、日々の忙しさや照れくささに流されて親孝行を後回しにしていると、いざ行動を起こそうとしたときには手遅れになってしまう、という教訓なのです。
現代の生活は何かと慌ただしく、仕事や家事、育児などで毎日があっという間に過ぎていきます。そのなかで「いつか時間ができたら」などと思っているうちに、大切な機会を逃してしまうことも少なくありません。ですが、親孝行とは特別なイベントではなく、日々のなかの些細な行動の積み重ねです。たとえば、短い電話で近況を伝えたり、「寒くなったから体に気をつけてね」と一言添えたメッセージを送ったりするだけでも、親の心は温かくなります。
また、家族との時間をわざわざ作るのが難しいと感じている方も、何気ない会話やちょっとした気遣いを意識することで、充分に気持ちは伝わります。遠方に住んでいてなかなか会えない場合でも、写真を共有したり、季節の贈り物を届けたりと、できることはたくさんあります。
大切なのは、「特別な日だから」ではなく、「今この瞬間にできることをやってみる」という姿勢です。大げさなことをする必要はありません。ほんの少しの思いやりを積み重ねることで、後悔のない親孝行が自然と形になっていくのです。
何する?例でわかる親孝行の形

ファミソラ・イメージ
「何かしたいけど、何をすれば喜んでもらえるのかわからない」という声はとても多いです。親孝行には正解がないからこそ、自分に合った方法を探すことが大切です。そこで、いくつかの実例を知っておくと、親孝行の具体的なイメージが湧きやすくなります。
たとえば、「外食に誘う」というのは非常に効果的な方法の一つです。親世代にとって、子どもと一緒にゆっくりと食事の時間を過ごせること自体が大きな楽しみになります。特に、普段は話す機会の少ない近況報告や、昔の思い出話を共有するにはぴったりの時間です。相手の好きな料理や行ってみたがっていたお店を選んであげれば、より一層気持ちが伝わりますよ。
また、「日常生活のサポート」も喜ばれる親孝行の形です。たとえば、親が苦手とするスマートフォンやパソコンの使い方を一緒に操作しながら教えてあげるのも良いでしょう。家電の設定やインターネットの接続など、ちょっとしたことでも親にとっては大きな助けになります。あるいは、庭の手入れを一緒に行う、重たい買い物の荷物を代わりに運んであげるなど、日常の中で役立つ行動も効果的です。
さらに、親がこれまで話したことのなかった昔の話を引き出す「思い出づくり」も心に残る親孝行になります。古い写真アルバムを一緒に見ながら、当時の出来事やエピソードについて会話をすることで、親の表情も自然と和らぎます。こうした時間は、ただの雑談ではなく、家族の歴史を共有する大切な機会でもあります。
大事なのは、どんなに小さな行動であっても、「あなたのことを思って動いているよ」という気持ちが伝わることです。身近なところから始めることこそ、長く続けられる親孝行の第一歩になります。
親孝行されて嬉しかったこと体験談

ファミソラ・イメージ
実際に親御さんが「嬉しかった」と感じた親孝行には、どのような共通点があるのでしょうか?多くの親御さんが口をそろえて挙げるのが、「気持ちがこもっていたこと」こそが、何より嬉しかったという点です。高価なプレゼントや豪華なイベントではなく、気持ちを込めた小さな行動が心に残るものとなるのです。
たとえば、「手紙をもらった」という体験談はとても多く聞かれます。手紙は、書く人の気持ちが文章に込められており、読むたびにその想いを思い返すことができる特別な贈り物です。また、「突然帰省してくれた」という例も、サプライズ性がありながらも、忙しい中で時間を作ってくれたという事実に、親は深く感動するようです。さらに、「孫の写真や動画を送ってくれた」ことが嬉しかったという声も多く、特に離れて暮らしている家庭では、日々の様子を伝えるだけでも安心感につながります。
そのなかでも、特に印象に残っているという意見が多かったのは、「一緒に過ごした時間」です。忙しい合間を縫ってでも顔を見せに来てくれたり、食事を共にしたりするだけで、親にとってはかけがえのない思い出となるのです。会話の内容やそのときの表情、何気ない出来事も、何年たっても鮮明に記憶に残ることがあります。それだけ、共有した時間には大きな価値があるのです。
大切なのは、どれだけ大きなことをしたかではなく、「どれだけ気持ちを込めたか」です。親孝行は見栄えや形式ではなく、真心が伝わることで、その価値が何倍にも広がります。ちょっとした行動の積み重ねが、親にとって何よりの喜びになっているということを、改めて心に留めておきたいですね。
気持ちが伝わるプレゼント選び

ファミソラ・イメージ
プレゼント選びは親孝行の定番とも言えますが、「何を贈ればいいのか分からない」と悩む方はとても多いものです。親の性格やライフスタイル、好みによって最適な贈り物は異なるため、選ぶ際には慎重な配慮が求められます。プレゼント選びのポイントとして大切なのは、「実用的であること」と「感謝の気持ちが伝わること」の2点です。
たとえば、毎日使える上質なタオルや、季節に応じたブランケット、クッションなどは、実際の生活に役立ちつつも、贈られる側に心地よさを届けられるため、非常に好印象です。さらに、親が寒がりであれば電気毛布や足元ヒーターなども検討できます。こうした実用品は「自分のことを気にかけてくれている」と親に感じてもらえる要素が強く、心が温まるギフトになります。
また、料理が趣味の親には、使いやすい調理器具や高品質の調味料セット、地域の名産品などもおすすめです。たとえば、包丁やまな板といった基本的な道具のほか、最新の調理家電を贈れば、料理の時間がさらに楽しいひとときになります。普段の生活のなかで使えるものほど、贈り手の気遣いを実感してもらいやすいのです。
贈る際には、ぜひ一言メッセージや手紙を添えてみてください。たった数行でも、手書きの言葉には特別な力があります。「いつもありがとう」「体に気をつけてね」といった優しい言葉があるだけで、贈り物の価値は何倍にも膨らみます。
一方で、健康機器のようなアイテムは、親に体の不調を意識させる可能性もあるため、選ぶ際には十分な配慮が必要です。事前に欲しい物をリサーチしたり、さりげなく希望を聞いておいたりすることが、相手にとって負担にならない贈り物につながります。
プレゼントに明確な「正解」はありませんが、もっとも大切なのは「あなたのことを思って選びました」という気持ちです。その心遣いこそが、親にとって何よりも嬉しい贈り物になるのです。
旅行 おすすめプラン3選を紹介

ファミソラ・イメージ
旅行は親孝行の中でも特に喜ばれる方法のひとつです。普段とは異なる環境で親子の時間を過ごすことによって、心の距離がぐっと縮まり、お互いの存在の大切さを再確認するきっかけになります。日常ではなかなか得られないリフレッシュ効果や、新しい発見もあるため、親子双方にとって特別な思い出となることでしょう。
まずおすすめしたいのが「温泉旅行」です。温泉地には静かで落ち着いた雰囲気があり、心身ともにリラックスできます。お風呂に入りながらゆったりと会話を交わせるのも、普段忙しい人にとっては貴重な時間です。また、旅館やホテルでは地元の旬な食材を使った料理を楽しめることも魅力の一つ。年配の親御さんにとっては、足腰に負担をかけずに過ごせる点も安心ですね。なお、宿泊施設を選ぶ際には、バリアフリー対応やエレベーターの有無などにも配慮して選ぶと、より快適な滞在が実現します。
次にご紹介したいのが、「季節の風景を楽しむ観光地」です。春の桜、秋の紅葉など、四季折々の美しい自然を眺めながらの散策は、心を癒す素晴らしい時間となります。景色を背景に記念写真を撮ることで、その瞬間を形として残すことができるのも嬉しいポイントです。加えて、季節ごとの風物詩や地域限定のスイーツなどを楽しむことで、五感すべてを使った思い出作りができます。
そして、「近場の一泊旅行」も親孝行として非常に効果的です。遠出が難しい家庭や、移動時間が長いと負担になるという場合には、住まいから1〜2時間圏内の宿泊地を選ぶことで、気軽に非日常を体験できます。たとえば、郊外の自然豊かな公園に併設された宿泊施設や、古民家をリノベーションした宿など、ちょっとした工夫で旅行感がぐっと増します。自宅に近い場所であっても、新鮮な空気と静かな環境のなかで親と語らう時間は、何よりの贈り物となるはずです。
旅行の計画は、親にとっても楽しみのひとつです。出発前から一緒に相談しながら日程や行き先を決めていくことで、当日だけでなく計画段階から親孝行が始まっているとも言えます。体調や食事の好みなどを考慮してあげると、より安心して楽しんでもらえる旅行になるでしょう。こうした心配りが、親にとっては何よりも嬉しいことなのです。
親孝行をしたい!何するか迷ったときは

ファミソラ・イメージ
- 親孝行アイデア ランキングTOP3
- 親孝行の日はいつ?できることリスト
- 会話と笑顔が生むあたたかな関係
- 無理なく続く親孝行のコツとは
親孝行アイデア ランキングTOP3

ファミソラ・イメージ
親孝行のアイデアにはさまざまな形がありますが、実際に喜ばれた行動として、ボイスノートマガジンが全国1056人を対象に実施したアンケート調査の結果をご紹介します。この調査では、「自分が親にした親孝行(子ども視点)」と「子どもにしてほしい親孝行(親視点)」という2つの立場から集計が行われており、それぞれの視点で異なる親孝行の形が見えてきました。
最も喜ばれた親孝行TOP3
第3位 孫の顔を見せる
両親にとって「孫に会えること」はかけがえのない体験です。実際に会うことが難しい場合でも、写真や動画を送るだけでも親にとっては大きな喜びとなります。
第2位 プレゼントを贈る
日用品やお菓子、衣類など、気持ちを込めて選んだ贈り物はやはり定番の親孝行。特に両親の好みに合ったものを贈ると、より喜ばれる傾向があります。迷ったときはカタログギフトも便利です。
第1位 一緒に旅行をする
もっとも多くの支持を集めたのが「一緒に旅行をする」こと。非日常の時間を共有することで、心の距離がぐっと縮まる体験となります。温泉旅行や自然豊かな観光地など、リラックスできる場所が人気です。
子どもにしてほしい親孝行TOP3
第3位 話し相手になってくれる
特別なことをしなくても、会話するだけで嬉しいと感じる親は多いです。日常の話や思い出話などを共有することが、心のつながりを強くします。
第2位 孫の顔を見せてくれる
子ども視点と同様に、親にとっても「孫と会うこと」は何よりの幸せ。実際に会えなくても、成長の様子を伝えるだけでも安心感を与えることができます。
第1位 元気な姿を見せてくれる
親にとって子どもが元気でいてくれることが、何よりも大きな安心と喜びになります。忙しくても体調や近況を知らせるだけで、立派な親孝行です。
視点の違いを知ることで、より効果的な親孝行に
このように、子ども側は「何かをしてあげる」行動に重点を置きがちですが、親側は「日常のつながり」や「元気な様子の共有」に価値を感じる傾向があることが分かります。この違いを理解することで、より心に響く親孝行を考えるヒントになるでしょう。
難しく考える必要はありません。自分が無理なくできることから始めてみることが、長く続けられる親孝行への第一歩です。
親孝行の日はいつ?できることリスト

ファミソラ・イメージ
8月8日は「親孝行の日」として知られています。この記念日は、1989年に親孝行全国推進運動協会によって制定されたもので、「パパ(8)」「ハハ(8)」という語呂合わせに由来しています。法律上の祝日ではありませんが、家族との絆を見つめ直すためのきっかけとして広く認識されるようになりました。あまり知られていないかもしれませんが、この日は親に対する感謝の気持ちを意識し、行動へと移す絶好の機会です。忙しい毎日のなかでは、「ありがとう」の気持ちを改めて言葉にする場面は少ないもの。だからこそ、こうした記念日が貴重なのです。
この親孝行の日には、特別な準備や高価な贈り物は必要ありません。たとえば、いつもより丁寧なメッセージを送る、少し時間を作って電話で話す、それだけでも親にとってはとても嬉しいことです。また、一緒に食事をする、家事を手伝う、買い物に同行するなど、日常的な行動の中で思いやりを示すことも、しっかりと気持ちが伝わる親孝行となります。「あなたのことを気にかけていますよ」という姿勢こそが、もっとも大切なのです。
この日を利用して「今度一緒に○○しよう」と未来の計画を立ててみるのもおすすめです。たとえば、今後の旅行計画を一緒に話したり、季節のイベントへの参加を約束したりするだけでも、親にとっては大きな楽しみになります。その日が訪れるまでの間も、会話や想像を通して親子のつながりを深めることができます。記念日とは単なる1日ではなく、その前後を含めた気持ちの共有の時間でもあるのです。
この記念日を機に、「なにかしてあげたい」という思いを行動に移してみましょう。難しく考える必要はありません。日常の延長でできることから始めることが、もっとも自然で心のこもった親孝行になるのです。
会話と笑顔が生むあたたかな関係

ファミソラ・イメージ
親孝行というと、つい特別な贈り物や旅行などの大きなイベントを思い浮かべがちですが、実は日常にある「会話」と「笑顔」こそが、最も大切な親子のコミュニケーションだといえます。意識的に特別なことをしようとしなくても、日々の中で自然に交わされる言葉や表情のやり取りが、何よりも心に残る親孝行になるのです。
たとえば、食卓での何気ない会話や、テレビを一緒に観ながらの雑談など、特別な話題がなくても、親にとってはその時間自体が嬉しいひとときになります。ときには、思い出話をしたり、最近あった出来事を気軽に話すだけでも、親の表情がほころぶことがあります。何気ない会話のなかに、親子の距離を近づける温もりがあるのです。
また、笑顔には言葉以上に気持ちを伝える力があります。笑顔で話すだけで、空気が柔らかくなり、相手の心にも安心感が生まれます。親子だからこそ、言葉にしなくても伝わると思い込みがちですが、やはり気持ちは、表情や言葉にしてこそ正確に伝わるものです。
親が年齢を重ねてくると、子どもとのちょっとしたやりとりが日々の活力になります。朝の「おはよう」や夜の「おやすみ」といったあいさつ一つでも、気持ちを通わせる大切なコミュニケーションになります。こうした習慣を重ねることで、自然とあたたかい関係が築かれていくのです。
どんなに忙しい日でも、たった数分間でもいいので、親と笑顔で言葉を交わす時間を意識してつくってみてください。特別な準備や大げさな演出はいりません。日々の積み重ねこそが、親にとって最も心に残る、かけがえのない親孝行になるのです。
無理なく続く親孝行のコツとは

ファミソラ・イメージ
親孝行は一時的なイベントではなく、できれば長く継続していきたいものですよね。瞬間的な感謝の気持ちを表すだけでなく、日々の暮らしのなかで自然に取り入れていくことが、より深い絆を育むカギになります。そのためには、「無理をしないこと」が最大のコツです。背伸びをせず、自分にできることから少しずつ始めていく姿勢が、長く続けるためにはとても大切です。
たとえば、週に一度の電話や、月に一回の帰省といった、日常生活に無理なく組み込める頻度をあらかじめ決めておくと、習慣として定着しやすくなります。気持ちや時間に余裕がないときに、無理に行動しようとすると疲れてしまい、それが継続の妨げになることもあります。気負わず、できる範囲で気軽に接することが、親子双方にとって心地よい関係を築く助けになります。
また、親からの「ありがとう」や「うれしい」という言葉をもらったとき、その反応が自分自身の喜びやモチベーションにつながることもあるでしょう。そのようなポジティブな循環が生まれると、親孝行はただの義務感ではなく、むしろ楽しく前向きな日課のひとつになります。さらに、ちょっとしたことでも親が喜んでくれるという実感が得られると、「次はこんなことをしてみよう」と自然と行動につながることもあります。
自分の生活スタイルやリズムを大切にしながら、親との時間をどう取り入れるかを考えることが大切です。たとえば、毎週末の買い物に付き添う、定期的に写真を送る、一緒にテレビ電話をするなど、小さな工夫ひとつで、親とのつながりを継続的に持つことができます。無理をしないこと、自然体で続けることが、結果として最も大きな親孝行になるのかもしれません。
前述のとおり、無理なく続けるためには親の健康にも配慮が大切です。厚生労働省が推奨する「健康づくりのための身体活動・運動ガイド」などを参考に、気軽に取り入れられる運動習慣を一緒に検討してみるのもおすすめです。
(参考:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド」)
親孝行をしたいが何するか迷ったときの総まとめ
最後に記事のポイントをまとめます。
- 親孝行は感謝の気持ちを行動で表すこと
- 小さな言葉や行動にも大きな価値がある
- 親が元気なうちに気持ちを伝えることが大切
- 食事や外食の時間を一緒に楽しむのが効果的
- 日常生活のサポートも親孝行の一つ
- 昔の話を聞きながら思い出を共有する時間が喜ばれる
- 手紙やメッセージが特別な贈り物になる
- 突然の帰省や電話も嬉しいサプライズになる
- 実用的で気持ちが伝わるプレゼントが喜ばれる
- 季節に合った旅行プランは記憶に残る思い出になる
- 親の体調や希望に配慮した旅先の選定が重要
- ランキングを参考にすると行動のヒントになる
- 会話と笑顔が日常の親孝行に直結する
- 親孝行の日を活用して感謝を伝える機会を持つ
- 続けやすい習慣化こそが無理なくできる親孝行になる