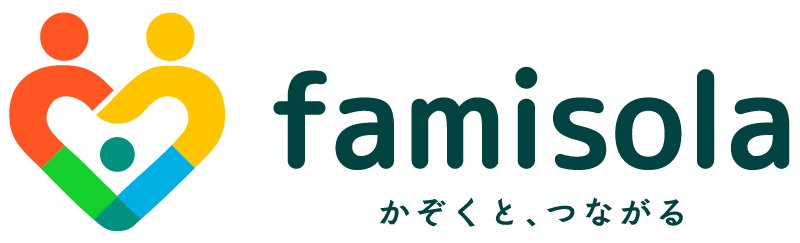日々の生活の中で、思い通りにいかないことは誰にでもあるものです。そんなとき、自分の感情に振り回されずに、穏やかに過ごせる人が身近にいると、「自分の機嫌を取るのが上手い人って、何が違うんだろう?」と感じることがあるかもしれません。一方で、少しの行き違いや期待が外れたときに不機嫌になってしまう自分に、ふと気づく瞬間もあるでしょう。
本記事では、「自分の機嫌は自分で取る」という考え方をベースに、日常生活の中で気分を整えるためのヒントをお届けします。職場での上司との関係や、家庭での旦那との会話、そして女性ならではの心の整え方など、多方面から具体的な対処法や機嫌の取り方を紹介しています。また、親との関係から学んだ感情のクセや、不機嫌になったときの直し方にも触れながら、実生活に活かせる工夫をまとめています。
無理に明るくふるまうのではなく、自分の気持ちを上手に扱い、少しずつでも心が軽くなるような選択肢を見つけていきましょう。感情との付き合い方を見つめ直すことは、自分らしく生きるための大切な一歩です。
- 自分の機嫌を整えるための具体的な習慣や工夫がわかる
- 思い通りにならない場面での感情の受け止め方がわかる
- 職場や家庭での人間関係における気持ちの扱い方がわかる
- 不機嫌な気分との上手な付き合い方や対処法がわかる
自分の機嫌を取るのが上手い人とは

ファミソラ・イメージ
- 自分の機嫌は自分で取るという思考
- おすすめの機嫌の取り方
- 職場で上司との接し方の工夫
- 女性ならではの気持ちの整え方
- 旦那との会話で笑顔を増やす
自分の機嫌は自分で取るという思考

ファミソラ・イメージ
自分の機嫌を自分で取るという考え方は、毎日の暮らしを心地よく、そして前向きに過ごすための土台となる大切な心の姿勢です。日常生活では、職場でのトラブルや家庭内のちょっとした行き違い、通勤途中の予想外の出来事など、思い通りにならないことがたくさんあります。そのたびに外側の状況や他人の言動に気分を振り回されていると、心が疲れてしまいますよね。だからこそ、「自分の感情は自分で選べる」「気持ちの舵は自分で握る」という意識が大切なのです。
自分の内側から気分を整える力を持っていると、どんな場面でも冷静さを保ちやすくなり、安心して自分らしくいられるようになります。たとえば、落ち込んでいるときには、目を閉じて深呼吸をゆっくり3回するだけでも、気分が少し緩みますよ。また、お気に入りの音楽を流してみたり、自然の風を感じながら短い散歩をしてみたりするのもおすすめです。
さらに、窓を開けて空気を入れ替える、温かいお茶やコーヒーをゆっくり味わう、香りのよいアロマを焚いてみるなど、感覚を心地よく刺激する工夫も効果的です。こうした行動はすべて、「自分の気分を自分で整える」ことにつながっています。気持ちを整えるのに、特別な準備や大きな変化は必要ありません。むしろ、日常の中でできる小さな習慣こそが、心にやさしく効いてくるのです。
こうした積み重ねが、自分の感情を丁寧に扱う姿勢につながり、気づけば毎日の景色が少しずつ、でも確実に明るいものへと変わっていきます。あなた自身のために、今日もひとつ、自分を大切にする時間を持ってみませんか。
おすすめの機嫌の取り方

ファミソラ・イメージ
機嫌の取り方には人それぞれの方法がありますが、大切なのは「自分に合ったものを見つけること」です。誰かの方法が自分に合うとは限りませんし、逆に、自分にとってしっくりくる方法は意外と身近なところにあるものです。たとえば、朝にお気に入りの飲み物をゆっくり味わう時間を作るだけでも、その日一日の気持ちが整う方もいらっしゃいます。香りや温度、味わいを丁寧に感じながら過ごす時間は、心の余白をつくり、自然と呼吸も深くなります。
また、夕方のタイミングで少し外に出て歩いてみるのも効果的です。仕事や家事の区切りとして散歩を取り入れることで、頭がすっきりし、気持ちの切り替えにもなります。天気や季節の移り変わりを感じるだけでも、ちょっとした癒やしになりますよ。
さらに、手帳やノートにその日のできごとや「今日のよかったこと」を書き出してみるのもおすすめです。特別な出来事でなくても構いません。「お昼に食べたパンが美味しかった」「子どもが笑ってくれた」など、小さな喜びを言葉にすることで、自分の一日を前向きに捉える練習にもなります。
ポイントは、時間や手間をかけることではなく、ほんの5分でも「自分のために使っている」と感じられる瞬間を持つことです。忙しい中でも「この時間は自分の心を整えるため」と意識することで、心の安定に繋がります。大切なのは、他人と比べず、自分の気持ちを優しく見つめる習慣を持つことです。
職場で上司との接し方の工夫

ファミソラ・イメージ
職場での人間関係、とくに上司とのやり取りはストレスの原因になりやすいものです。上司の言動ひとつで一日中気分が揺れ動いてしまう、そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし、少しの工夫で気持ちの持ちようや対応の仕方を変えることができれば、過ごしやすさはぐっと高まります。
まず意識しておきたいのは、「相手に過剰な期待をしないこと」です。上司に対して「こうしてくれるはず」「分かってくれるはず」と思い込みすぎてしまうと、期待が外れたときに落胆や苛立ちが大きくなってしまいます。そのような感情の波を少しでも穏やかにするために、自分がコントロールできる範囲に目を向けることが大切です。
たとえば、日頃から報告・連絡・相談(いわゆる報連相)を丁寧に行うこと、相手の反応や性格に合わせて言葉を選んで伝えることなど、自分なりに意識できる工夫を積み重ねてみましょう。また、忙しいときや感情が高ぶりそうなときには、一呼吸おいてから話す、少し間を取って落ち着いて行動するというのも、職場内の人間関係を円滑にするためのポイントになります。
もちろん、無理をしすぎないことも忘れてはいけません。どれだけ気を遣っても、どうしても通じないと感じる場面もあるかもしれません。そんなときは「自分はできることをやった」と割り切ることも、心を守るひとつの方法です。
気分が疲れてしまったときには、視点を少し変える工夫もおすすめです。たとえば、「今日はここまでよく頑張ったな」と自分をねぎらう時間を意識的に作ったり、信頼できる同僚と他愛もない会話を交わすことで、気持ちがふっと軽くなることもあります。自分の心のゆとりを大切にしながら、職場での人間関係に向き合っていけると良いですね。
女性ならではの気持ちの整え方

ファミソラ・イメージ
女性は日々の生活の中で、仕事・家事・育児など多くの役割を同時にこなしている方がとても多く、それぞれに求められることが違う分、心のバランスを取るのが難しくなることがありますよね。特に、家庭内と職場の間で切り替えがうまくいかないときや、自分の時間がなかなか取れない状況では、心の余裕がなくなりがちです。そんなときこそ、自分自身に対して「これでいいんだ」と優しい言葉をかけてあげることがとても大切です。完璧を目指すのではなく、今の自分をそのまま認めることで、心がほっとする瞬間が生まれます。
また、自分を癒すための小さな習慣を日常の中に取り入れていくことも効果的です。たとえば、お気に入りの香りを部屋に取り入れることで、気分がリセットされたり、お風呂にゆっくり浸かって一日の疲れを洗い流す時間を確保するのもよいですね。読書が好きな方なら、ほんの10分でも好きな本の世界に浸ることで、現実の忙しさから一歩距離を置くことができます。
そのほかにも、照明を少し暗くして落ち着く空間を演出したり、お気に入りのカップでお茶を飲むといった、ほんのわずかな「自分のためのひと手間」が心の落ち着きにつながります。自分に合った方法を見つけることが一番大事です。
「整える時間」は、目には見えにくいけれど心の中に空白と余白をもたらしてくれる大切なものです。ほんの数分でも、自分と向き合う時間を持つことで、心がじんわりとほどけていきます。そうした積み重ねが、毎日の生活をより豊かに、そして自分らしく彩ってくれます。
旦那との会話で笑顔を増やす

ファミソラ・イメージ
家庭内でのコミュニケーションは、心の安定や日常の雰囲気に大きく影響する要素のひとつです。とくに旦那さんとの会話がスムーズにいくことで、気持ちにゆとりが生まれ、家庭全体の空気も柔らかくなると感じる方も多いのではないでしょうか。夫婦間のコミュニケーションが円滑であると、自然と笑顔も増え、安心感が生まれてきますよね。
大切なのは、「完璧な会話」や「正しいやり取り」を求めすぎないことです。日々のやりとりの中で、あれこれ考えすぎると気が重くなってしまいます。まずは、ちょっとした出来事を気軽に共有することから始めてみましょう。たとえば、「今日こんなことがあってね」とテレビや外出先での出来事を話したり、「これおいしかったよ」と感想を共有したりするだけでも、会話のきっかけになります。
また、感謝の気持ちを言葉にするタイミングを意識することも、関係性をよくするポイントです。「ありがとう」「助かったよ」「おつかれさま」といった一言は、相手の気持ちを和らげ、より良い雰囲気をつくってくれます。
もちろん、無理に話そうとしなくても大丈夫です。会話は自然なタイミングで交わされるのが一番ですし、まずは自分がリラックスしている状態であることが大切です。たとえば、落ち着いた時間帯に話しかけてみたり、お互いの好きな話題を意識して取り入れてみるなど、気楽にできる工夫を取り入れてみましょう。
ときには話がうまくかみ合わないこともありますが、そうした瞬間にも柔らかい気持ちでいられるよう、自分のペースを保つことが大事です。夫婦の会話を気負わず、笑顔のきっかけを少しずつ増やしていくことで、家庭の中の空気がよりあたたかく、心地よいものになっていきますよ。
自分の思い通りにならないと不機嫌な人

ファミソラ・イメージ
- 親との関係で学んだこと
- 不機嫌な時の対処法とは
- 機嫌の直し方を工夫する
- 病気ではなく気分のクセを理解する
- 自分を見つめ直す時間を持つ
- 家族と幸せを共有する工夫
親との関係で学んだこと

ファミソラ・イメージ
親との関係性は、子どもの頃から現在に至るまでの自分の行動や感情のパターンに強く影響を与えていることが少なくありません。子どもの頃に繰り返し見てきた親の態度や接し方、そして家庭内でのコミュニケーションのスタイルが、そのまま自分の中に染みついているケースはよくあります。たとえば、親がいつも自分の感情を優先し、周囲に気を配ることが少なかった場合、そういった姿勢を無意識に真似てしまうことがあります。それが大人になってからの人間関係や物事の捉え方に影響を及ぼすこともあるのです。
しかしそれに気づくことができれば、自分の行動を変えていくための第一歩になります。「これは親の影響かもしれない」と一歩引いて見つめることで、自分自身の思考や反応をより客観的に理解できるようになります。そこから、「今の自分はどうしたいのか」「どんな関係を築いていきたいのか」といった、自分自身の意志に基づいた選択をしていくことが可能になります。
また、親との関係を振り返ることは、自分を責めることでも、過去を否定することでもありません。むしろ、過去を受け止めることで、今の自分に対する理解が深まり、未来に向けてより柔軟な考え方を育てるきっかけになります。「ああ、こういう反応は親ゆずりかもしれないな」と気づけたその瞬間から、自分の感情に対する新たな選択肢が生まれてくるのです。
親子関係の中に隠れている心のクセや思考の偏りを優しく見つめることで、無理なく自然に、自分をより良い方向へと導いていけるようになります。こうした気づきの積み重ねが、日々の暮らしを少しずつラクに、そして穏やかに変えていく大切なヒントになるのです。
不機嫌な時の対処法とは

ファミソラ・イメージ
誰しも不機嫌になってしまうときはあります。日々の忙しさや思い通りにいかない出来事、気候の変化や体調など、さまざまな要因が重なることで、気分が沈んでしまうことは誰にでも起こり得ます。そうしたときに大切なのは、その不機嫌を無理に否定したり抑え込もうとするのではなく、「今はちょっとしんどいんだな」と素直に受け止めることです。それだけで、心が少し軽くなることもあります。
不機嫌な状態を受け入れることで、自分に対して優しい気持ちを持てるようになります。そして、その感情が外に出る前に、いったん立ち止まって冷静になる時間を持つこともとても効果的です。たとえば、深呼吸をゆっくり3回してみたり、静かな場所に移動して自分だけの空間をつくってみるのもひとつの方法です。自分の感情を無理に変えようとせず、今の気持ちに少し距離を置くことで、自然と落ち着きが戻ってきます。
また、頭の中でぐるぐると巡る思考を紙に書き出してみるのもおすすめです。自分の感じていることを「言葉にして外に出す」だけでも、不思議と心が整ってくることがあります。ノートにただ気持ちを書くだけでも、自分との対話が深まり、自分を客観的に見る手助けになります。
自分に合った対処法をあらかじめいくつか持っておくと、いざというときに不機嫌な気分に飲み込まれることなく、自分らしさを保つことができるようになります。気分に振り回されるのではなく、気持ちと上手に付き合うための工夫をしていくことが、毎日を穏やかに過ごすための大切な鍵になるのです。
深呼吸などの簡単なストレス対処法は、厚生労働省の『健康づくり』ページでも紹介されています。
(参考:厚生労働省「腹式呼吸をくりかえす」)
機嫌の直し方を工夫する

ファミソラ・イメージ
前述の通り、不機嫌な気持ちになってしまうのは誰にでもあることです。そのうえで大切なのは、どのように気分を切り替えて、自分のペースを取り戻すかということです。感情が揺れること自体は自然なことですが、その後の対応次第で一日の質や人との関係性も大きく変わってきます。
自分の機嫌を上手に直すためには、気分転換の“引き出し”をいくつか持っておくと安心です。たとえば、好きな音楽を聴くことは、その瞬間の気分をガラリと変えてくれることがあります。気分に合った曲を選んで、数分間だけでも音の世界にひたる時間を持つことで、頭の中がリフレッシュされます。また、香りを楽しむのもおすすめです。お気に入りのアロマを数滴垂らしたティッシュを手元に置いたり、芳香スプレーを空間にひと吹きするだけでも、気持ちがすっと和らぐことがあります。
さらに、軽くストレッチをして体を動かすことも効果的です。肩を回したり、首をゆっくり伸ばすような簡単な動きでも、血流が促されて気分が変わることがあります。とくに座りっぱなしの時間が長い方には、体を動かすことが心にも良い影響を与えます。
他にも、手を動かす作業を取り入れてみるのもひとつの方法です。料理や掃除、ちょっとした手芸や工作など、無心で取り組めることは心の整理にもつながります。また、外に出て少し歩いてみることで、空気や景色の変化が刺激となり、自然と視野も広がっていきます。
ポイントは、「機嫌を直そう」と強く意識しすぎないこと。頑張って切り替えようとするほど、逆に疲れてしまうこともあります。そうではなく、「今はこういう気分だけど、ちょっとだけ違うことをしてみようかな」という軽やかな気持ちで取り組むことが大切です。そうすることで、ふとした瞬間に気がついたら少し笑顔が戻っていた、そんな自然な流れをつくることができますよ。
病気ではなく気分のクセを理解する

ファミソラ・イメージ
不機嫌な状態が続くと、「自分はおかしいのではないか」と不安になることがあります。感情の波が大きいと、自分を責めたり、必要以上に落ち込んでしまったりすることもあるかもしれません。こうした気持ちの変化には、日々のストレスや生活環境、思考のクセなど、さまざまな要因が関係していることがあります。
ただし、日常の中で感じる気分の揺れに対しては、まず「気づくこと」から始めてみましょう。たとえば、何かが思い通りに進まなかったときに怒りや不満が出てしまうのは、「自分の中の期待と現実とのギャップ」による自然な反応かもしれません。また、人によっては嫌なことがあるとすぐに黙り込んだり、周囲と距離を置いたりするなど、反応の仕方が異なるのも当たり前です。こうした「感情のクセ」は、多くの場合、これまでの経験や育った環境、習慣などによって形成されています。
心理学でも、こうした反応パターンを客観的に見つめることが、セルフケアの第一歩とされています。「またこのパターンが出たな」と気づけるようになると、感情に飲み込まれずに冷静な視点を持ちやすくなります。これは感情を言語化する「ラベリング」という手法とも重なります。感情に名前をつけて整理することで、心が落ち着きやすくなるという研究もあり、自分自身を理解する助けになるとされています。
ただし、長期間にわたって強い落ち込みや不安が続くような場合には、無理をせず、専門の医療機関やカウンセラーに相談することも大切です。自分一人で抱え込まず、信頼できる人に話してみることも新たな視点や安心感につながることがあります。
大切なのは、自分の感情を否定せず、少しずつ理解していこうとする姿勢です。その意識が、心を穏やかに整え、自分らしい過ごし方へとつながっていきます。
自分を見つめ直す時間を持つ

ファミソラ・イメージ
毎日の忙しさに追われていると、自分の気持ちにじっくりと向き合う時間を確保するのはなかなか難しいものです。仕事や家事、人付き合い、さまざまなタスクをこなしているうちに、一日があっという間に過ぎてしまうこともありますよね。ですが、そんな慌ただしい日々の中にこそ、ほんの少しでも「自分を見つめ直す時間」を意識して取り入れることがとても大切です。
たとえば、朝起きてすぐの時間や寝る前の10分間だけでも、静かな空間に身を置いて、自分の気持ちと向き合う時間を作ってみてください。「今日の自分はどんな気持ちだったかな」「何に心が動いたかな」と丁寧に振り返ることで、自分の感情の流れに気づくきっかけになります。慌ただしく過ごしていると見逃してしまいがちな「小さな気持ちの変化」に目を向けることで、心の声に耳を傾ける習慣が少しずつ育っていきます。
さらに前述の通り、その日の中で「うまくできたこと」「気持ちがモヤモヤした場面」「心が軽くなった瞬間」などをノートに書き出してみるのも非常に効果的です。言葉にすることで気持ちが整理され、自分自身を客観的に見る視点も持てるようになります。書き出すことは、頭の中にある漠然とした感情に形を与える行為でもあり、思っていた以上にスッキリする感覚を味わえることもあります。
このような「自分を見つめ直す時間」は、一日の締めくくりとしても、翌日のスタートを整えるためにも役立ちます。心の動きに気づく力を少しずつ育てていくことで、自分に優しくなれたり、他人との関わり方にもゆとりが生まれるようになります。忙しさに流されがちな日常の中だからこそ、自分自身と向き合う時間を大切にしていきたいですね。
家族と幸せを共有する工夫

ファミソラ・イメージ
どんなに忙しい日々の中でも、家族と過ごす時間は心の支えになります。仕事や家事に追われていると、つい時間に追い立てられるように感じることもありますが、そんなときこそ、家族と過ごすひとときが、気持ちを落ち着けてくれる大切な時間になるのです。とくに意識したいのは、「小さな幸せを共有すること」です。何も特別なイベントでなくても構いません。たとえば、美味しいごはんを食べたときに「これ美味しいね」と声をかけるだけで、食卓にあたたかい空気が流れます。
一緒にテレビを見ながら同じタイミングで笑ったり、映画を見終わった後に感想を語り合ったりするだけでも、家族の距離がぐっと縮まります。ときには、「今日はありがとうね」「助かったよ」といった感謝の言葉を口に出すことで、相手の気持ちを和らげ、自分自身の気持ちも優しくなります。言葉にすることで、お互いの存在が自然と大切なものとして感じられるようになるのです。
また、日常の中でちょっとした出来事を共有することも、家庭の雰囲気を和らげるポイントになります。たとえば、子どもが学校で話してくれたエピソードを皆で聞いたり、誰かが見つけた面白い話題をシェアしたりすることで、会話のきっかけが増え、笑顔も増えていきます。特別な何かを用意しなくても、ただ一緒にいる時間を楽しむだけで、家族の絆は深まっていきます。
家族と笑顔で過ごす時間は、自分の心を満たしてくれるだけでなく、相手にも穏やかさや安心感を届けてくれます。そんな積み重ねが、忙しい毎日の中にあたたかさを育み、家庭という空間を心のよりどころとしてくれるのです。
総括:自分の機嫌を取るのが上手い人と自分の思い通りにならないと不機嫌になる人
最後に記事のポイントをまとめます。
- 自分の感情は自分で選べるという意識を持っている
- 深呼吸や散歩など簡単な習慣で気持ちを整えている
- 外的要因に左右されず内側から気分を立て直している
- 朝や夕方に心を整える時間を意識的に取っている
- 日々の小さな出来事に喜びを見つけられる視点を持つ
- 書き出しによって思考を整理し気持ちを客観視できる
- 自分に合った気分転換方法をいくつも持っている
- 職場では相手に過度な期待をせず関係を工夫している
- 他人と比較せず自分の状態を優先して受け入れている
- 家庭内では感謝や共感を言葉で表現し雰囲気を和らげている
- 感情のクセや反応パターンに自覚的である
- 不機嫌なときでも自分を責めずに受け止めている
- 自分と向き合う静かな時間を日常に取り入れている
- 家族との日常を通して小さな幸せを共有している
- 落ち込みや不安が長引く場合は専門家に相談する柔軟さがある